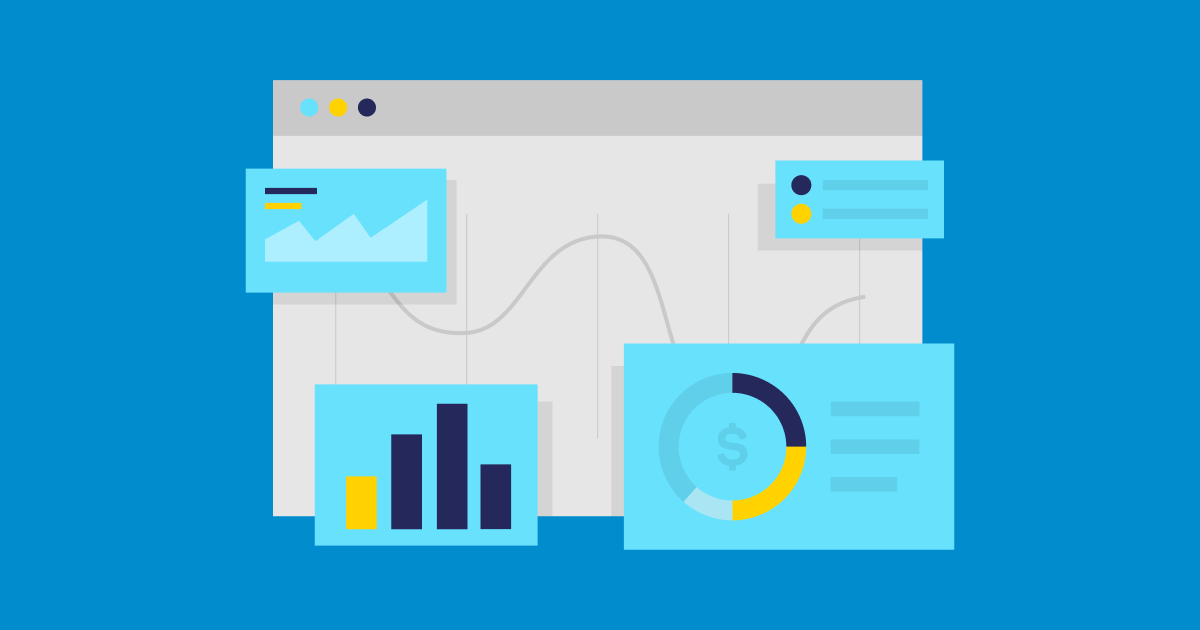中小企業がDXツール導入で失敗しないための、ベンダーやコンサルタントの見極め方

近年のDX化の波に乗り、大手企業は社内のDX人材や外部企業を活用しDXを推し進めています。しかし中小企業では、DXツールを導入しようにも、社内に知見を持つ人材が不足しており、外部のベンダーやコンサルタントの選定に苦心しているケースが多いようです。
そこで今回は、DXツールのカスタマイズや導入をサポートするベンダーやコンサルタントの見極め方について解説します。
DXツールの導入を成功させるには、初期の「ベンダー選定」が極めて重要
DXを推進する場合、まず自社にマッチしそうなツールを選定し、カスタマイズや導入をサポートしてくれるベンダーやコンサルタントを探す企業が一般的です。しかし、DXに知見を持つ大手企業と異なり、中小企業ではDXツールを導入しようにも、「どのベンダーやコンサルティング企業を選んでいいのか分からない」という悩みを抱えるケースが少なくありません。
そのため、導入予定のツールベンダーにパートナー企業を紹介してもらうという企業も増えているようです。ただし、パートナー企業は紹介してくれたツールベンダーが提供するサービスを使うのが前提になります。もし他社のツールの方がマッチしていたとしても、パートナー企業から他社サービスの推薦をしてもらえる可能性は少ないでしょう。
また、現在多くの企業や自治体で問題になっているのが「ベンダーロックイン」です。ベンダーロックインとは、特定のベンダーやSIerにシステム開発を任せた結果、機能が複雑化してしまい、リプレイスや自社での保守が困難になる問題を指しています。公正取引委員会が2022年に実施した調査によると、「既存ベンダーと再度契約することとなった」と回答した官公庁は98.9%にも及んでおり、一番多かった理由は「既存ベンダーしか既存システムの機能の詳細を把握することができなかったため(48.3%)」という回答でした。
出典:「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書」https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/feb/220208_system/220208_report.pdf
システム開発の領域では、一度ベンダーを決めて作り込んでしまったら、保守を含めて他社に依頼することが難しくなります。ベンダー選定に失敗し、使われないツールを作ってしまった場合、開発したベンダーしか仕様が分からないため作り直しができない、減価償却が終わるまで使いにくいシステムを使い続けDXとは程遠い状態になる、使われないために減損処理をせざるを得なくなる、といった悪循環やリスクが生じます。DXツール導入は、最初のベンダー選定とツールの作り込みがとても重要。「ツールベンダーに紹介された」という理由だけで、外注先を決めるのは避けましょう。
DXの成果を出すなら、業務設計が得意なベンダーがお勧め
DXツールの導入を検討している企業の中には、既存の業務を新しいシステムに移植しようとして、技術力に優れたSIerや開発会社を選定するケースも多いようです。既存業務の移植が目的であれば問題はありませんが、本来のDXは、デジタル技術を用いてビジネスモデルを変革し、新たな価値を創出することです。業務の見直しを行なわないまま新しいシステムを構築しても、業務のデジタル化は実現できますが、事業を成長させるような効果を出すことは難しいでしょう。自社の独自性や要望を全てシステムに反映した場合、機能が複雑化してコストがかさみ、現場のメンバーも使いにくくなるというリスクが考えられます。
企業のDXでよくある「5つの間違い」とは? DXがうまくいかない理由を解説
https://www.gl-navi.co.jp/library/contents/page/U2sje32Z
DXツールの導入によって、生産性を向上させ成果を上げたいのであれば、自分たちの業務に合わせて複雑なシステムを構築するのではなく、既存業務をツールに合わせて再設計する必要があります。近年はノーコードツールが登場し、エンジニアでなくても社内でシステム構築ができるようになりました。シンプルな設計にすれば、コストをかけずにスピーディに構築できる上に、運用、保守もしやすいというメリットがあります。グローバルで実績のあるデファクトスタンダードのDXツールを導入すれば、ベストプラクティスが確立されているために、失敗するリスクを抑えられるでしょう。
そのため、DXツール導入のベンダー選定は、システムの開発実績だけに着目せず、上流工程の業務コンサルティングも含めたソリューションを一緒に模索してくれる企業を選ぶと良いでしょう。DXツール導入のベストプラクティスに知見があり、「業務設計が得意」という観点で判断することをお勧めします。また、説明が分かりやすく使い方がイメージできるコンサルタントを選びましょう。専門用語を多用して難解な説明をするコンサルタントに任せてしまうと、実際にツールを使う現場メンバーにも同じように説明するため、理解を得られずに、せっかく導入したシステムが使われなくなってしまいます。
CRMを用いた営業活動や採用活動などで効果を出す場合は、導入するツールが入力しやすく、現場で受け入れられることが大前提になります。導入するシステムが会計や購買、在庫や生産管理に紐づくERPであれば、システムへの未入力が大きな問題につながるため、現場は確実に入力します。しかし、CRMはERPほど未入力がクリティカルなリスクにはつながりません。Excelの管理でもビジネスが回ってしまうため、必ず入力するような業務設計と、入力しやすいシンプルなシステムが、DXツール導入を成功させるカギになります。
2社以上のベンダーを比較し、セカンドオピニオンとして活用を
前述した通り、比較検討をせずにツールベンダーに紹介してもらった企業にそのまま依頼するのはリスクが伴います。選定の際は、必ず自社でもベンダーを探して相見積もりを取りましょう。相見積もりを取れば、コスト観点のメリットだけでなく、ツールベンダーからの紹介のような制約がないので、「A社ではなくB社のツールの方が御社の課題にはマッチします」といった、セカンドオピニオンとしてのフィードバックを受けられます。最低でも2社以上のベンダーを比較して、依頼する企業を選定しましょう。
なお、ベンダーやコンサルティング企業は1社のみに絞る必要はありません。技術力に優れたベンダーと、業務設計のベストプラクティスを持つベンダーの2社に依頼し、得意分野によって使い分けるという方法もあります。
GLナビゲーションは、社内でもSalesforceを中心としたCRMを活用しており、営業活動に効果的な業務設計とDXツール導入の実績が豊富です。創業以来、人材育成や社内研修などのサービスを提供しているため、DXのコンサルティングに加えて、現場メンバーへの導入サポートも得意分野です。DXツールの導入を検討している場合は、セカンドオピニオンとしてご活用ください。
無料Salesforce診断も実施していますので、ぜひご相談を!
関連記事